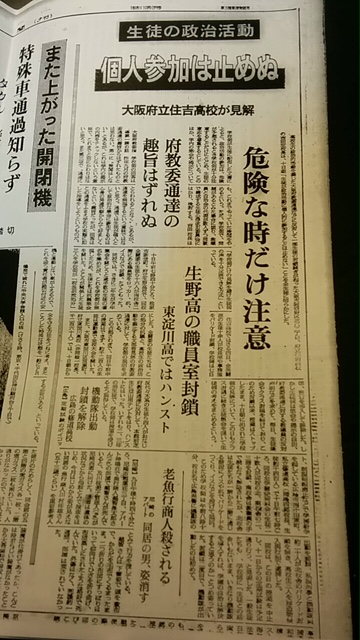
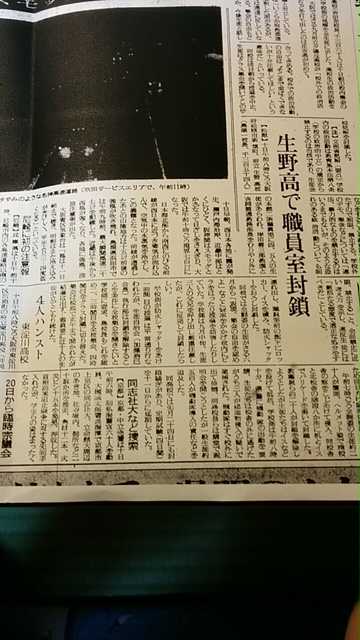
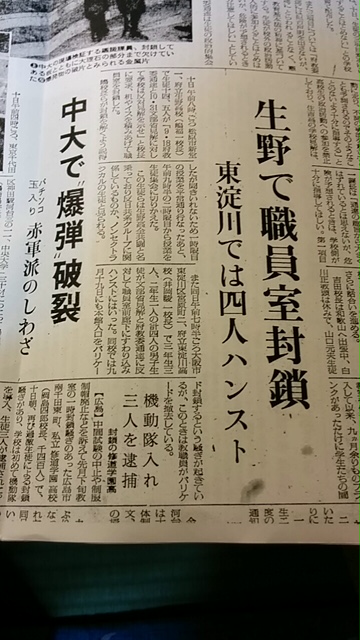
���̕��͂́A�u���E�S���������v�Ҏ[�ψ����̎��⎆�\�ɉ����ď����܂����B
�@1960�N��̊w���^���͂Ȃ����̂��H
��������Ώۂ́F
�l�j�I�ɂ́A���̍��Z�����̂Q�N���̎��ɋN�������w�������́A���t�W�c�i����̐��j�ւ̍R�c�ł������Ǝv���܂��B�S�Ă̋��t���Ώۂł������킯�ł͂���܂��A�����Ď������̖��������Ă��ꂽ�����������킯�ł����A�����̋����A�Ƃ�킯���������͐킢�̑Ώۂ������Ǝv���܂��B�܂��A�w�Z���x���鋳��ς�k�ւ̎��_�A�Ǘ��I�ȗl�X�ȋK���⋳���������Ă���l���������A�킢�̑Ώۂł������ł��傤�B
�Ƃ��낪�ʔ������ƂɁA���̋��t�W�c�ւ̋��e�����͌��݁A���k�̋��t�]���Ƃ��ď\�N�قǑO����A���P�[�g�����̌`�Ŏ��{�����悤�ɂȂ�܂����B����͒N�����x�v�����̂��m��܂��A�w��������̐��Ɏ�荞�݁A���̐��_���������ɂ��ĕ\�����͖���I�ɂ���Ƃ�������Љ�̏X���ȑ��ʂ�@���ɕ\���Ă��܂��B���t�Ɛ��k�Ƃ������͂̔�Ώ̐����������ł���̂ł͂Ȃ��āA�w�Z���\�����邷�ׂĂ̍\�����̐����I�ȍ��c�Ƃ����`�Ԃ������߂�ꂽ���̂������̂ł����A�������������x����鑤�̐l�Ԃ͍��C�̂���c�_�̏��ݒ肷�邱�Ƃ����ۂ������Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A��������邱�Ƃ͎���̐��x��j�邱�ƂɂȂ邩��ł��傤�B
������Ώۂ͂��ꂾ���ł͂Ȃ��ł��傤�B���������������Ăǂ��ł��ł����A���l�Ȑl�Ԃ������Ă��邱�̐��E�ł��ꂼ�ꂪ�v�����ꂵ����f���ɕ\������t���b�g�ȋ�Ԃ����݂����A�����̐����҂ƌ��S�҂���ɂ������낵���v���オ�����X�L�[���ƋK���Ő��E���o���オ���Ă���Ƃ������Ƃł��B�����Č������Ɣ\�͎�`�ɂ���Ă������E�͈ێ��ł��Ȃ��Ƃ������{��`�I�����ɂ��d�ꂵ���ł܂��܂����E�͐l�Ԃ������Ԃ��Ă����ł��B�����͂���Ȏd�g�݂Ȃǒm��R���Ȃ���������ǂ��A�����炭�����I�Ɋ����Ă������̂ł����B����͂�����u���ԁv�ƌĂ����̂ł��傤���A����Ɛ���Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B
����������R�́F
�������̍ݐЂ��Ă������썂�Z��1968�N�ɁA�ꕔ�̑̈狳�����Ǝ҂Ɩ������ă��x�[�g��������Ă����Ƃ������Ƃ��\�I����܂����B�����̔��[�͂�������ł����B���̎��͎�����ʓI�Ȑ��k�ŁA���̖\�I�����R�N�������̗E���ȍs�ׂɐG������A�Љ���ւ̋����������n�߂܂����B69�N��1���ɂ͂��̗L���ȓ�����c�u���̓���������A�w����������l�Љ�ւ̍R�c����������̐g������čs���Ă��邱�Ƃ�m��ɂ��A�܂��܂����炩�̍s�����K�v���Ɗ�����悤�ɂȂ����킯�ł��B
�ŏ��́A�Љ��茤����i���₱��Ȗ��O�̃N���u�͑��݂��Ȃ��悤�ł����j�Ƃ����N���u�֓���A�����悤�Ȗ��ӎ��������Ԃ����邱�Ƃ�m��܂����B�����āA���ԂƂƂ��Ɋw�Z�̌��{�̐��ւ̔ᔻ���J�n���܂����B
���N���i�ǂ�ȑg�D���j�^�������[�h�����̂��H�F
�ŏ��́A�w�Z�̗l�X�ȋK���ւ̔ᔻ����n�܂�A���k�V���ւ̌��{�Ɗw���Ղւ̉���ɑ��čR�c�����Ă����܂����B�Ќ��ł͊w���Ղň��ۂ̖��␅���̖��Ȃǂ����グ�A���������Ԃ𑝂₵�Ă������Ǝv���܂��B�������A�w�Z���̉͂̂�肭���Ƃ������̂ŁA����ɚ��������܂���ł����B���̔N��11���Ɏ��B�Ќ��̗L�u���閧���Ɂu�S�w�����ψ���v��g�D���A�w�Z�������v�悵�܂����B���[�_�[�͎O�N����E�N�ł������A�ނ̌���10���قǂ̒��Ԃ��W�܂�A10�������ɐE���������܂����B
���������͈�T�ԑ����܂����B�A���A�Z��őS�w�W����J���A�������̑i����S���k�ɘb���A�����W�c�ւ̗v�����f���Đ킢�܂����B�����̊w�����[���x���܂ōZ��Ŏ������̘b���Ă���܂����B���̓��X�̂��Ƃ͎��̑S�l���̒��ōł��l�Ԃ��M���ɑ������̂��Ƃ����m�M�����܂ꂽ�u�Ԃł����B
| �q�E����������`����V���r | ||
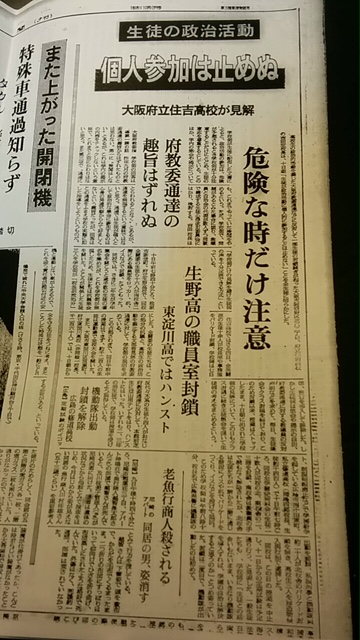 |
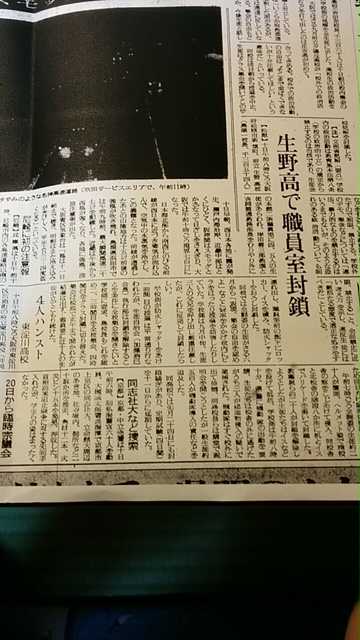 |
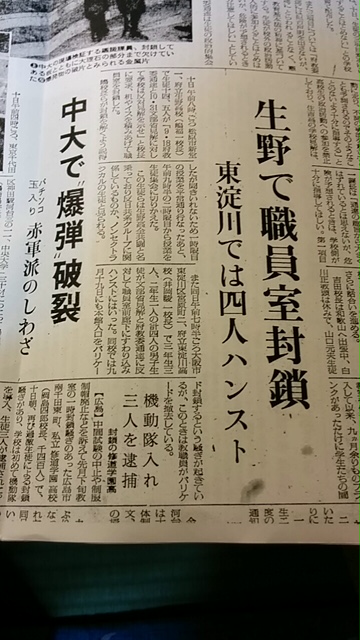 |
��60�N���ۂƂ̘A�����̗L���F
60�N���ۂ͎��̋�̎��̏o�����łقƂ�ǒm��܂���B��ɒm���Ƃ��Ă͒m�邱�ƂɂȂ�̂ł����A���ۂ̈��ۓ�����m��Ȃ�����ɂƂ��Ă͘A�����ȂNJ������܂���ł����B
60�N���ۓ����̐��_�Ǝ���������̓����̐��_�Ƃ͂��Ȃ�̋���������悤�Ɋ����܂��B60�N���ۂ̂��Ƃ������ł����m�蓾�Ȃ����ɂƂ��Ă͊��Ⴂ�����邩������܂��A���̎���̓����͐����I�ۑ肪�͂����肵�Ă����Ǝv���܂��B�Ε]������Y�J�̓����Ȃ�50�N�����̐킢���������Ƃ͂����A60�N�̈��ۓ����͂͂�����Ə��j�����œ_������Ă��܂����B�����āA���̎��_�ŏ���j�����邽�߂̓����Ƃ͐��蓬���ł����Ȃ������ƍl���܂��B����ɔ�����60�N�㖖�̎������̓����͂��������L�͈͂ȕ����I�ŎЉ�I�ł������I�ł����铬���������ƍl���܂��B50�N����������ۂ֎��铬���́A��㖯���`�����甽�����֓]�����A�@�ێY�Ɓ^�ΒY�Y�Ƃ���d���w�Y�Ɓ^�Ζ��Y�ƂւƓ]������ߖڂł��������ƂŁA�Љ�I�ϓ������ۏ��ɏœ_������Ă����܂������A60�N�����̊w���̓����͍��x�o�ϐ������ɂ����ĘJ���҂̌o�ϓ����͏I���ǖʂɂ���A�ނ���Љ�I�Ȗ�������s�����Ă������ゾ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������A�S�w�A�n�}�h�͒P�Ȃ���p�������ł͂Ȃ����{�]�����̂��̂��ÂɎ������Ă������A�S�����͎Љ�̂��̂̍��ւ���ڎw���Ă����Ǝv���܂��B�����͂��̂��Ƃ��͂�����ƈӎ����ł��Ă��Ȃ�������������܂��A���哬���Ɠ��哬��������������̂́A���͂̒��_�ł��銯���g�D�����Ƃ̂�����Ɩ��ԁ��s���Љ�̋��K�܂݂�̐��Ԃւ̍R�c�Ƃ��ē�d�̓��{�Љ�ւ̍R�c�^���ł������ƍl���܂��B
�A�^���Ɋւ��_�@�A�v�z��
���i�w��w�i�w���j��I���R�i�i�w�̓��@�j�F
���Z�i�w�͂����Ȃ�ƂȂ��ł��傤�B���w�̂قƂ�ǂ̐��k���i�w���钆�ŋ^����������i�w��I�т܂����B��w�i�w��1972�N�ł��i����w�j�B�Ȃ���w�i�w�����̂��͂͂����肵�܂���B�����A���e���獧�肳�ꂽ���炾�Ǝv���܂��B�e�ƊW�͂���قLj�������܂���ł����B���̍��Z�ł̊����ɂ������������Ă���܂������A���̂Ƃ��덂�Z2�N���̔N�ɗ��N�����ē�x��N�����o�����Ă��܂����A���ɐe�����߂��͂��܂���ł����B
�������Z�Ő�����F�l�����ɂ͍��Z���o�Ă��������ɍs�����҂��������A��w�i�w���邱�ƂɎ�̌��߂����͂���܂����B�����Œʂ�Ȃ���Γ����ɍs������ł͂����̂ł����A���܂��ܒʂ��Ă��܂������ƂŁA����s����i�w�����Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B
�������T�[�N���F
��ɂ��������悤�ɍ��Z�ł͎Љ��茤����ő����̂��Ƃ��w�т܂����B���́A��N���̎��͉����N���u�ł������A���ڂ̓�N���̎��ɂ͐��k��̖��������܂����B���̑��ɂ͔��p�N���u�ɂ��o���肵�Ă��܂����B
��w�ł́A��N���i72�N�j�̎��Ɂu���㒆��������v�ɓ���܂������A����قǔM�S�Ȋ����Ƃł͂���܂���ł����B�O�N���ɂȂ��Ċw���̎�����Č������i69�N�̑S�����^���̌��ʁA�w��������͏��ł��Ă��܂����j�Ɋւ���Ă���͂���Ȃ�ɔM�S�Ɋ������܂����B�����A���R�������T�[�N���A���S�̂Ŏ��g��ł��܂����̂ŁA�����ɂ������ւ��܂����B������Č����ꂽ��́A�Ȃ����ψ����ɉ�����āA���̌�l�̎��Ɋw��l�グ�����Ɋւ��A���̉��ŋ��s�⎠��̑�w�Ƃ����t���������邱�ƂɂȂ�A����Ȃ�ɓ}�h�Ƃ��ւ��܂������A�����͊w���͒��j�h�ƃu���g�n�̓}�h�����āA���ꂼ�ꂻ��Ȃ�̊W��ۂ��Ă��܂����B
���̏������Ă����Љ�w���͒��j�h���哱����\�ʏ㈬���Ă��܂������A������͔ނ�Ǝ�����āA�O���˓�����S���Ƃ��������ŋ������邱�ƂɂȂ�܂����B�ꉞ�A������͑�w�������o�b�N�A�b�v�����Ă��āA�u���g�n�Ƃ������Ƃŋ������\�������̂ł��傤�B
���Ǐ��̌��Ȃǁi���t�A��y�A�������A�������I���O�����l���Ȃǁj�F
�l�j�I�ɂ́A���w���̍����������`�ɂ͊S������A�T���g����J�~���Ȃǂ�ǂ�ł��܂����B���Z2�N�̎Ќ��ɓ���܂ł͐����I�Ȃ��̂͂قƂ�NJS���Ȃ������Ǝv���܂��B�ǂ��炩�Ƃ����ƕ��w�N�ł����B�L���P�S�[����o�r�����X�A�g���X�g�C��h�X�g�G�t�X�L�[�Ȃǂ𗐓ǂ��Ă��܂����B
2�N���ɂȂ��āA�ɂ킩�ɐ����I�ȕ�����ǂނ悤�ɂȂ�܂����B��y�⒇�Ԃ��犩�߂��āA�}���N�X�E���[�j���֘A�̕�����ǂނ悤�ɂȂ�܂����B�}���N�X�͓�����āA���̎��͂قƂ�Ǘ������Ă��܂���ł����B��ۂɎc���Ă���̂̓��[�j���́w���ƂƊv���x��W�����E���[�h�́w���E��h�邪�����\���ԁx�G�h�K�[�E�X�m�[�́w�����̐Ԃ����x�Ȃǂł��傤���B
���ɑ���ȉe����^�����l�Ƃ��Ă͉��t��M�搶�����܂��B�ނ͎������S���ς̑S�Ă̂��Ƃ��T�|�[�g���Ă���Ă��܂����B�������Z�𑲋Ƃł����̂����t�̂������ł��B�ނ͐�シ���̖����`���v���ɋ��E���g���Ő擪�ɗ����ē����Ă��������ŁA�ё�`�҂ł����B�ނ��璆���v���Ɋւ������F�X����������̂ł��B�����F�D����̗��������Ă����Ǝv���܂��B
���ɐ�������F�����������l��l�ƖS���Ȃ��Ă���̂Ŏ₵������ł����A�������l�Ƃ͔N�Ɉ�x��x����Ƃ�����A�I���̗F�ł���܂��B
��w�ł́A�w�����Љ�w�ł��������ƂŁA�a�O�_�n�̏�����ǂނ��Ƃ����������悤�ɋL�����Ă��܂��B�}���N�[�[��t�����N�t���g�w�h�n�̂��̂Ɓw���{�_�x�Ȃǃ}���N�X�n�̂��̂Ƃ���s���ēǂ�ł��܂����B
���e����^�����l���i�������I���O�����l���Ȃǁj�F
�I���O�����l���Ȃǂ͂������܂����Č����܂���B�N�����l�I�ɐ������悤�Ƃ����o���͂���܂���B�����A�w���ւ̓��荞�݂�W��ł̉����Ȃǂ͉��x���o�����܂����B���X�A�S���ς͑g�D�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA����Β��ԏW�c�ł����̂ŁA�ʂɁu�j�́v������킯�ł��Ȃ��A���R�ȏW�܂�ł����B
���푈����ł��闼�e�Ƃ̊W�F
���͕��m�Ƃ��ē���֔h������A�X�}�g���ŏI����}���܂����B�����{�A���Ă��āA��ƌ����������Ő��т������܂����B���m�a�т̎Ј��ŕ��ʂ̃T�����[�}���ł��B��͐�Ǝ�w�ł��̂ŁA���̓T�^�I�Ȋj�Ƒ��ł��B���͈�l���q�ł��̂ŁA�O�l�Ƒ��ł��B���͐�O�ɗ��e�𑁂��ɖS��������J�l�ł��B��l�̎o�Ɉ�Ă�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�������A�ǂ���玄�Ɠ����ŕ��w�N�ł������悤�ŁA�t�����X���w�ɌX�|���Ă����悤�ł��B�Ƃɂ̓o���U�b�N�S�W��}���������̖{�Ȃǂ�����܂��B�܂��A�����I�ɂ͐�O�̐N�ɂ��肻���Ȋv�V�h�Ŗk��P��q�g���[�Ȃǂ̖{���ǂ�ł����悤�ł��B���͎Љ�}�̉E�h���������Ă��܂����B
��ɂ������܂������A�e�Ƃ̊W�͗ǍD�ł����B������������������悤�ɂȂ��Ă��A���̗����������Ă���܂����B���Ƃ̉�b�͂���قNJo���Ă��܂��A�ނ����^�_�҂ł������悤�Ɋ����Ă��܂��B������Ɛ��̒����߂Ɍ��Ă����悤�ł��B�ނ̈��Ǐ����i��ו��i�S�W������܂����j�ł����̂ŁA�Ȃ�ƂȂ��킩��悤�ȋC�����܂��B
��͑��̋����Ń������X��Ђ��c�ވ�Ƃ̖��ŁA��O�͑傫�ȉƂɏZ��ł����悤�ł��B�푈���͒W�H���֑a�J���A��オ��P�ŋ^���ԂɂȂ�̂������Ƃ悭�b���Ă���܂����B�푈�ɂ�鏝���͂����ɂ����邱�Ƃ��ł��܂��B���̉����Ȃ�����Ɍ������āA�{�l�I�ɂ͋�J�����Ƃ����v���͂���܂����B��シ���A���A���Ă������A�H����S�ĂȂ��Ȃ��Ă��ďĂ��삪���ł������Ƃ������Ƃł��B���ɂ͂悭�푈�̘b�����Ă���܂����B�푈���ɔ��튈�������Ă�����w�����̂���ŏZ�ݍ��݂̂���`����������Ă��������ŁA�u�푈�͕�����v�Ƌ����Ă�����Ăт����肵�����A���̒ʂ�ɂȂ����Ƃ������Ƃ����x���b���Ă��ꂽ�̂���ۂɎc���Ă��܂��B�m���l�ւ̃��X�y�N�g���������悤�ł��B
������̋�C�i���ۓI�A�Љ�I�A�����I�Ȏ���w�i�j�F
�����̓x�g�i���푈���������������A�w���^��������ł�������A���̒����Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ƃ����C���͍������傫�������Ɗ����܂��B�܂��A���傤�ǎ�ҕ���������܂ł̂��̂Ƃ͈���ĖڐV�������̂ɉf���Ă��܂����B�ČR�̂�������i�ŃW�[���Y�₸���܂ȂǃJ�[�L�[�F�̐��i�����s���Ă��܂����B���y���r�[�g���Y�̒��������s��A�����L���Ă��܂����B�����I�ɂ͗l�X�Ȃ��̂������፬���ɂȂ��Ă������ゾ�����悤�Ɏv���܂��B�������͐��������ۂ��āA�W�[���Y�ɉ��ʂ𗚂��ēo�Z�������̂ł��B�������Z�̃o���J���ƃA�����J���������������悤�Ȏp�ł����B
���R���邱�Ƃ���҂̓����ł���悤�Ȏ���ł����B������l����A��l������������r�I���e���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����炭�A�܂����Ă��Վ���̋L�����������Ɏc���Ă��鎞��ŁA��O�̋K�͂�ے肵�Ďn�܂��������{�̐V���ȃX�^�C����͍����Ă���悤�ȃ��N���N����悤�Ȋ������������ƋL�����܂��B���݂̂悤�ȑ��ꂵ�������ł͂Ȃ��A�ꂵ���Ƃ�������M���邱�Ƃ��ł���悤�Ȏ��ゾ�����Ɗ����܂��B���X�ƐV�������������܂�A�����g���A������`����}���N�X��`�ֈڂ�Ȃ�����A�����I�ɂ̓r�[�g���Y���W���Y���h���I�ł��������A�}�C���X��R���g���[�����悭�����܂����B�܂��A�A���O������Ȃǂ����s�肾���A�A���_�[�O���E���h�I�ȕ��������͓I�Ȃ��̂Ɍ����Ă�������ł��B
�B�}�h���ɂ���
���}�h�Ƃ̊ւ��i�l�I�ȓ}�h���A�w���Ƃ��Ă̓}�h���j�Ƃ��̕]��
���Z����̓}�h�ƌ����Ă��A����قLjӎ��������̂ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B�S���ςɂ͔��퍂���ɓ����Ă����҂��������A�x���A��t�����g�Ȃǂ̊����Ƃ����܂����B�����g�͂��܂肻�����������I�ȓ}�h�����ӎ��������Ƃ͂���܂���ł����B��w��������Ə�̐���̊����ƂƂ̐ڐG������܂������A�ނ�̘b�́u�������Ȃ��v�Ǝv�����Ƃ͂����Ă��g�D�I�Ȋ����ɓ��荞�ނ��Ƃ͂���܂���ł����B��͂��{�͍��Z�����ł����B�m���A70�N���ۓ����̎��͑S���ς̃����o�[�̓t�����g�̃o�X�œ����֍s�����̂������悤�ɋL�����Ă��܂��B���͍s���܂���ł������B
��w�ł́A��ɂ��������悤�ɒ��j�h�ƃu���g�����܂����B���j�h�ɗU���āA��̍��ɓ����֍s�������Ƃ��o���Ă��܂��B���̓��������������ł͊��S�ɖY��܂����B�u���g�ɂ��U���ĎO���˂։��_�ɍs���܂������A�����Ŏ��g�������ɑ̗͂��Ȃ����v���m��܂����B����Ȗ�ł����������t�������͂�����̂̑g�D�ɂ͓���܂���ł����B�l�̍��Ɋw����̉��Ŋ��̂������̑�w�Ɗւ�邱�ƂɂȂ�܂������A���̎��A���u�Б�w�̑S�w���ɗU���ď����ȃT�[�N���ɓ���܂������A��������Ƃ��Ă����Ɏ��R���ł��Ă��܂��܂����B
�m���ɓ}�h�̑g�D�͑�w���̉^������ߐ��ł���̂ɔ����Čp����������̂ŕK�v�ł���Ɗ������܂����A�����̓}�h�̗��_�͍�����l����A���Ȃ薢�n�Ȃ��̂ŁA��w�����̌p���I�őg�D�I�ȓ����ɗL�v�ł��������ǂ����͋^�킵�����̂�����܂��B�}�h�̑g�D�I���Q���D�悳��āA�ʑ�w�ł̉^���̌p���ƈێ��ɂǂꂾ���𗧂������͒肩�ł͂���܂���B
���l�̓u���g�n�̐l�������玑�{��`�ᔻ�̏d�v�����w�����Ă��炢�܂����B70�N�㒆���ɒ��ڂ̊ւ�肪�Ȃ��������̂́A�ԕ�h�̉|�����_�ɂ͌X�|���Ă��܂����B
���^�����ɑΗ������g�D�Ƃ��̕]���F
���Z�����őΗ������g�D�͂���܂��A�l�I�ɂ͉��l���̐��k�������ɔ����āA�W��ɎQ�����Ȃ������悤�ł��B
��w�ł́A�w�����ɑΗ����Ă����g�D�́A�E�h�n�̏����A������{���Y�}������܂����B��x�A�w���ŏ�銈�������Ă���E���ɍR�c�ɍs���āA�Ԃ蓢���ɂ����ĕ����҂��o�����Ƃ�����܂��B�܂��A�T�[�N�����������ł̗l�X�ȗ��Q�Η��͓���I�ɂ���܂����B�l�I�ɂ͈�x�^�T�[�N���̐l�ɑ�w���Ńi�C�t�ŏP��ꂽ���Ƃ�����܂��B�K���A���̐l�͛������荘�������̂Ŗ��������邱�Ƃ��ł��܂����B
���}�h�����^���͕K�R���������F
�}�h�����Z�����ɉ�����Ă���Ƃ����o�������Ă��܂���̂ŁA�悭������܂��A����69�N10���ɓ����ő傫�ȓ���������A�}�h�̐l�Ԃ͓������������Ă����悤�ł��B���̎���������n��̍��Z�ł́A����������Ēn���ŕ������������邩�A�����̒��������ɍs�����ŔY�l�������Ƃ����b�͕��������Ƃ�����܂��B���Ȃ݂ɁA����11���̕��������͓���̐��Z�œ��������̕����������N����܂����B�����A�N��������̂��Ǝv���܂��B�N�Ƃ͒m��܂��B
�����Q�o�ɂ��āF
���Q�o�͎�����w�ɓ����Ă���o�����܂����B���ڂɂ͊W���܂���ł������A���j�Ɗv�}���̓��Q�o�Ŏ��l���o�܂����B�����g�́A�w���ʼnE���n�̏W�c�ɒ��Ԃ����ꂽ�̂����Ă��܂��B�܂��A���g���g�D�I�ȑΗ��Ōl�I�Ȗ\�s�ɉ�܂������A�t�Ɏ������̃T�[�N�������ɓG���Ă���Ǝv�����l�����P���������Ƃ�����܂��B����́A���炩�ɃR�~���j�P�[�V�����s���ł��傤�B�g�D�Αg�D�̓��Q�o�͘H���̈Ⴂ����Ƃ��������A������Ƃ������������ŋN���闘�Q�Η�������I�Ȏ�����[���ɂ��āA���O��d�Ԃ�����Ɋ�Â����̂ł���Ɗ����Ă��܂��B����͂ǂ̎Љ�ł��N���肤�邱�Ƃł��傤���A��͂苷���W�c�ł������قǁA���ꂪ�X���悤�Ɏv���܂��B�����ɊJ���ꂽ�g�D���̐S���������Ă��܂��B�����{�g�D�ƂȂ�Ƃǂ����Ă����ƌ��͂̉����h�����߂ɕ��I�ɂȂ�X��������܂����A�����炭���̂悤�Ȕ����{�����┽�̐��������J���ꂽ�g�D�Ƃ��č\�z���邱�ƂŊ��x���s�k���Ă����o�������邩��ł��傤�B���̈Ӗ��ł́A���{���邢�͑̐��������|�I�ɗL���ł��邱�Ƃ͊m���ŁA���̂悤�Ȑ�p���x���̓����͌���I�Ȃ��̂��Ƃ����̂����P�ł��B�����̐�p��g�D�h�q�H���Ő��̒����ς����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�m�邱�Ƃ͏d�v�ł��B���̈Ӗ��ł͓��Q�o�͑傫�ȋ��P���Ǝv���܂��B���{�̔��̐��^���̈��́u�s��v�̋��P���Ǝv���܂��B�������ׂ��ł��B
������A���̔ߌ��ɂ��Č�鎋�_������悤�ł��B����́A�����̍R���͋ɂ߂Č��n�I�ȕ��@���Ƃ��Ă��邱�Ƃł��B�ߑ��̂悤�Ȕ�ѓ���͎g��ꂸ�A�����̌����̂悤�ȓ��e��̂悤�Ȍ`�Ԃ��قƂ�ǂł��B�����Ăɂ��ւ�炸�A�����̂悤�Ȍ����̃��[���̂悤�Ȃ��̂����݂��܂���ł����B�ނ���A�ߑ��̑�ʎE�C���v�킹��悤�Ȏc���Ȗʂ��������킹�Ă��܂����B���~�߂������炸�A����Ƃ����Ӗ��ł�����͖ڂɗ]��l����悵�Ă��܂����B����͂���Ӗ��ł�20���I�̐푈�ł��������̂ł��傤�B�z�u�Y�{�[�����w20���I�̗��j�x�Ŏw�E���Ă����悤�ɁA�`�͌��n�I�ł����̖{���͋ߑ�I�Ȑ��_�ōs���Ă����̂�������܂���B�W�I�ƂȂ����Ώۂ͓}�h�̊����Ƃł͂���܂������A����͂܂��ɐE�ƕ��m�ւ̂���ł������A����Ɏ��ӂ̃V���p�ɂ��y���Ƃ��l�����킹��ƁA�ߑ�ɂ����閯�O�ւ̖����ʍU����z�N��������̂ł�����܂����B�����̂��Ƃ��l�����킹��ƁA���̓��Q�o�̔ߌ���20���I�̊v���v�z�̂����郌�[�j���I�Ȉ�Y�ł��邩������܂���B���̂Ȃ�A�ނ͓}�h���ł����������E�Ɗv���Ƃ̑g�D�Ƃ��Č`����������ł��B����͒鐭���V�A�ɂ�����e������g�D��h�q������̂ł������Ƃ͂����A���̌`�Ԃ������̊v����ڎw���g�D�̖͔͂Ƃ��Ȃ�܂����B60�N��Ƃ�������ɋN�������`���ł̔��v����{���r�A�ł̃Q�o���̐킢�ɐG������Ă��������̎�҂ɂƂ��Ă͓��R�̋A���ł�������������܂���B�����A�����Ԃ��̔ߌ����J��Ԃ��Ă��̎��㐫�ɋC�t���Ȃ������Ƃ������Ƃ͐[�����P�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��ƍl���܂��B
�C�w���^���̐��ʂ͂��������H
���w�����A�w���O�ł̐��ʂ̗L���i�����I���ʂ��܂ށj�F
���Z����Ɏ��������s���������ۂ��ȓ����́A���̊w�N���琔���ē�قnj�܂ł͑����܂����B�������̉��̊w�N�̎҂��������̓������p�����āA�������R�������Ɏ��g�݁A���R�����������܂����B�������A���N���ĕ��̕ւ�ɂ��A���̐����֖߂��������ł��B�����炭�A�F�X�����]�Ȑ܂��������̂ł��傤���A�������̐���̕����͒����͑����Ȃ������悤�ł��B
�w�Z�Ƃ������͎��X�Ɛ��オ��シ��ꏊ�ł��B�����Ă����͍��ƂƐ��{���Ǘ�����ꏊ�ł���A������Ǘ����鋳�E�������͍��Ƃ̌ق��l�ł��B����ȏ��ŁA�ꎞ�I�ɒʉ߂���҂ł����Ȃ���X�ɂ͓����̕��������������邱�ƂȂǂł���͂�������܂���B�X�Ɍ����Ȃ�A���ƂɂƂ��Ė��҂ł����Ȃ���X�̓������������ƌ��͂�p���Ă��킶��ƒׂ��ɂ�����Ȃǂƌ������Ƃ͎��ɗe�ՂȂ��Ƃł�����ł��傤�B�����A���������ł��邱�Ƃ͂��̓����̕����̈�Y��`�����邱�Ƃ��炢�ł��B���Ƃ������Ȕ͈͂ł����Ă��q�⑷��߂����҂����Ɍ����`���邱�Ƃ��A�ł��邱�Ƃ̍ő�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B�����ۑ�Ƃ����Ӗ��ł́A�����͂������Ǘ�����҂��������������܂Ȃ���Ώ\���Ȑ��ʂ͓����Ȃ��Ƃ������Ƃł�����܂��B����������͉��X�ɂ��ē����̉s����݂点�鏊�Ȃɂ��Ȃ�܂��B���̑�������v���������ɍ������āA�ő�̐��ʂ邱�Ƃ�ڎw�����������̖ړI�Ȃ̂ł��傤���A�N�Ⴂ�w����k�ɂƂ��Ă����]�ނ͖̂���������܂��B�w�������̗��j�I�ȈӋ`����ߐ��ł������Ƃ����͖̂�������ʂ��Ƃł��������Ƃ������Ƃł��傤�B
�w���^���Ƃ����傫�ȎЉ�I�o���������{�Љ�ɗ^�����e�����������ꂱ�ꌾ�����ƂȂǂł���͂�������܂���B�����A�������̐��オ�o���������ꂱ��̕����̕\�w�́A��ɐ������ꂽ�`�Ő��_���������ƂȂ��č��������Ă��܂��B��҂̓W�[���Y������A�W���Y���A�A���O�����������Ă��邩������Ȃ����A���̎���̔��R���_�͎p����Ȃ������悤�Ɍ����܂��B���邢�́A����͎��̊��Ⴂ�ł����āA�S��������`�ň����p����Ă���̂�������܂��A�N���ɂ͂Ȃ��Ȃ������ɂ������̂ł�����܂��B
�����ʂɂ��Ă̔��Ȃ��邢�͋��P�F
�u70�N�V���b�N�v�Ƃ������t������܂��B���F�p���껏G���̒����ɂ́u7�E7�ؐ��̍����v���_�@��70�N��ȍ~�V�����s���^�������ꂽ�Ƃ���܂��B�m���ɁA�����Q�^������^���A�����ʉ^���⏗���^���A��Q�҉^���ȂǓ��{�Љ�����Ă�������܂ł̌�������Ă����l�X�ȎЉ��肪���o���܂����B����͊m����60�N���̊w�������̔������Ȃ���ΐ��܂�Ȃ��������̂�������܂���B���݂̐l���^����x�����h�̉^���Ȃǂ������������p���ł��邱�Ƃ͊m���ł����āA���̔���p�ł���i�V���i���Y�������͂ł͂�����̂́A��R�����͐₦�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���̈Ӗ��ł͋M�d�Ȉ�Y���c�����̂�������܂���B
�����A���P�Ƃ������̂��l����Ƃ��肷���邮�炢����ł��傤�B���̈�Ԃɋ�������̂́A�����I�p�t�H�[�}���X�����̎���ɂ͊X��������w���̐苒�����ŕ��������Ă��܂����B�V�h�̃t�H�[�N�L��̂悤�ȍL��苒�����i2010�N��̐��E�I�Ȑ苒�����̐��`�Ԃł����j�͋��R���܂ꂽ���̂ł����āA�ӎ��I�ɂ͍��܂���ł����B�܂��A�������x���ł̃p�t�H�[�}���X�͊F���������悤�Ɏv���܂��B���̂悤�ɍL���R�~���j�P�[�V�����̉�H���Ȃ���������ł͂���Ƃ͂����A��O�̎���̐��������ƂƂ̐���I�f��A���o�I�Ȓf��͑傫�Ȃ��̂������悤�Ɏv���܂��B����͎��������o���ĘJ���^���ɎQ�������Ƃ��ɒɊ��������̂ł��B�������̑O�̐���͐��̖��剻���������l�X�ł��B�ނ�ޏ���̖����`�ɑ��銴���͂���قǎ������ƕς��Ȃ��̂ł����A�g�D�̘b�⓬���̎d�����߂���c�_�ɂȂ�Ƒ傫�ȈႢ������܂��B���̐���̐l�����͐�㖯�剻�����ŏ����������ʂ���낤�Ƃ�������X��������܂��B�m���ɐ��̖��剻�����̗��j��m��Βm��قǁA��ȓ������������Ƃ�������܂��B�Y�J�̓�������g�����߂��铬���Ȃǐ�̌R����Ԃ�����ǖʂ����邮�炢��ł��������ƂŁA���ǂƂ̎���ɂ���ď��������킸������̐��ʂ���낤�Ƃ���C�����͕�����܂����A���̂悤�ȗ�����ɂ���ē������ʂ������ɐƂ����̂ł��邩�͗��j�������Ă���Ă��܂��B���č]�ˎ���̔_���Ꝅ���v���ł͂Ȃ��āA�̎�ւ̂��肢�ł��������Ƃ͂悭�m��ꂽ�����ł��B�_���̐��肪�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�Ꝅ�w���҂͎a���Ƃ����p�^�[�����J��Ԃ���Ă��܂����B���̖��O�̒�R�Ǝx�z�҂Ƃ̊W�͍��������Ă��܂��B�J�����c�̉����̃p�^�[���͏�ɂ��̌`�Ԃł��B�K���A�w���҂����ق���J���g���͖ʓ|���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
��㖯�剻�����̘J���^�����ʂ��猩��Ȃ�A���݂ł͂��̐��ʂ̂قƂ�ǂ����Âɂ���Ă��܂��B���̐ӔC�̈�[�͉^���̐��ʂǂ̌����ʂɈˑ��������āA�@�I�Ȋm�łƂ����g�g�݂��`�����邱�Ƃ�a���ɂ��Ă�������ł͂Ȃ��ł��傤���B����Ȃ����r���[�ȑg�D��������c���Ă��ւ̂��ς�ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂����̊��z�ł��B
�����80�N��̘J�퓝������铬���Łu�A���v�ւƋz������Ă����������g�������ł͌���e���Ȃ��p���N���Ă��邱�Ƃ��l����A�Ⴆ�����Ƃ͂����ߑ�����邱�Ƃ̕����^�̓����̓`�����p������Ƃ������ƂɂȂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�D�w���^����i���ƌ�j�ǂ��������H
���J���^���Ȃǐ����̒��Ŋw������̖₢�Ƃǂ��������������H�F
���Z�𑲋ƌ�A��w�i�w���A�����ŃT�[�N���^���Ɋւ��A�u���㒆��������v�⎩����A�w�������ȂǂŊ��������B��w�ł͋��R������w������������B�ǂ�����吨�̊w�����W�܂��K�͂ȏW��s��ꂽ���A���ɂƂ��Ă͂��܂�ɂ������̊w�����W�����邱�ƂŕԂ��Ă��ꂼ��̊炪�����Ȃ��Ƃ������o���������B����Ƃ����W�c�����邱�Ƃ̓���������A�w���ł̐����I�U�镑�����Ɍ˘f�����������B���Ȃǂ͉^���̈�[��S���������ł͂��������A�������Ŏ��������������Ɉׂ��ׂ����ɔY�B�B��̐��ʂƂ��Ă͂���܂łȂ������w����������Č����A�Ȃ���Ȃ�ɂ����̌��y�����������p���ł���āA80�N�㏉���܂ł͑��������悤���B
���ƌ�͏����Ȓ�����ƂɏA�E���A����̓��̘J���ɏ]���������A�呲�Ƃ������Ƃʼnc�Ƃɉ�A�����̐��ɍ����Ă��Ȃ����ƂɋC�Â��A�ސE�����B�����Ă�����x���E�ے���ʐM��w�Ŏ�蒼���āA2�N�Q�l���ď��w�Z�����ƂȂ�A���]�Ȑ܂��Ȃ����������N�܂ŋߏグ���B���Ԃ�ސE�������A���E�ɏA�����Ƃɒ�R���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��������A���łɌ������Ďq�����Y�܂�Ă����̂ŁA�����̂��߂Ɗ�����ċ������������B
��������ɂ͘J���g�������ɂ͔M����ꂽ���A�����ł������ǂ������͂��������B���ɁA80�N��̘J���������ɏ����đg�D���ŕ����������N����A�A���ւ̓����֔������A����ł̊�����Ղ���邱�Ƃ��ɂ��Ȃ��瓥�݂Ƃǂ܂����B�J���^���̊�{�͌���ł̒��ԂƂ̉�b��ւ��ł���B�������A�����ł��V���������Ă���V�l�����Ƃ̗����������邱�Ƃ������Ȃ����B�����I�Șb���������A����̗��Q�ɂ��Ă��l�I�ȏ������d��X��������A�g�D�łȂ�Ƃ�����Ƃ����������ǂ�ǂ�p��Ă������B�ސE�ԍۂɂȂ��đ��̒n�ɈېV�̉�o�ꂵ�A�ނ炪����֕��f���������݁A����܂ł̑��̋����̓����̈�Y�͎����ׂ���Ă������B����ɂ́A����̓��������ł͂ǂ����悤���Ȃ����E�������Ă���B�����炭����́A���č��Z�œ��������Ɋ����������I���E�Ƃ������̂Ɠ����ł���Ǝv���B
�����̌�̓}�h�Ƃ̊ւ��Ƃ��̕]��
��w�𑲋Ƃ��Ă����̎����͂܂��}�h�Ƃ̊ւ�肪����A���x���W��ȂǂɎQ���������A���J�������Ɖƒ됶���Ƃ����S�ƂȂ肻��قǔM�S�ɂ͎��g�߂Ȃ������B�}�h���g��80�N��ȍ~�����ׂ��Ă������悤�Ɋ�����B���_�I�ȌÂ��������Ă����B���ɁA���E�I�ȋ��Z���{��`����ƂȂ��Ă������ŁA���������I�ȉۑ肾���ł͂Ȃ����E�I�ȓ��������g�̐����ɖ��ڂɊւ���Ă��鎞��ɂȂ������Ƃ�A���E�I�Ȑl���^���ւ̗l�X�ȌX���Ƒ��l�ȗ��_������n�߂����Ƃ��A�����̓}�h������������Ă��Ȃ��Ǝv��ꂽ�B90�N��̃\�A����ȍ~�͂܂��܂������������悤�ɂȂ����B
���݂͐̂̊����Ƃ����̏����Ȍ�����ɎQ�����Ă���B�l�ł͂Ȃ��Ȃ����E�̏���ŐV�̗��_�I�Șb��̂͌��E������̂ŁA���ȂȂ���Q�������Ă�����Ă���B
���^�����Ԃ̂��̌�̊����ɂ��āi��������n���āj
���Z����̒��Ԃ͂��ꂼ�ꎩ�������̎d���ւƕ��U����āA����N�Ɉ��x������I�ɉ�����ł���B�ނ�ޏ�����܂��C���͍��Z�����ƕς��Ȃ��ɂ��Ă��A�Љ�^���ւ̉�H���f����Ă��邵�A���ꂼ��Ȃ̒u���ꂽ���ꂩ�����Ă���Ǝv���B
��w����̗F�l�������܂��J���^����Љ�^���֓��荞��ł���҂����邪�A���Ɠ��l�ɔY�ݑ����ۑ������Ȃ��畱�����Ă���B����҂͘J���^���A����҂͐����^���A����҂͎s���^���ւƎU��U��ɂȂ���A���ꂼ��̗���Ŋw������̐��_��ێ����Ă���҂������B�m���ɁA���ɂ͊��S�ɗ����ς��āA��Ƃ̊Ǘ��E�ւƏ��l�߂��҂�����ɂ͂��邪�A���R������킹��@��ɐڐG��������邱�Ƃ������̂́A�����ނ�ޏ�����܂����߂������̂�����Ă��邩�炾�낤�B
�E�����_�̎v�z�ɂ���
�������_�ɂ�����u�Љ��`�v�̕]���Ƃ��̗��R�F
���O�Ƃ��Ắu�Љ��`�v�u���Y��`�v�Ɋւ��Ă͍����l�X�̒��Ƀ��[�g�s�A�Ƃ��Ďc�葱���Ă���Ɗ�����B�������A20���I�͎����Ƃ��Ắu�Љ��`���Ɓv�����݂��A���ꂪ���S�ɂ����s�������Ƃ��܂������Ƃ��đ傫���B90�N��Ɏ��Ȃ�ɂ��Ẵ\�r�G�g�A�M�̗��j���w�ђ��������Ƃ����邪�A���X�Ɩ��炩�ɂȂ���j�I����������ɂ�āA���[�j�����뜜�����悤�ɉ��B�v�����s�k�������ƂŘc�߂�ꂽ���V�A�v���̎p���ɁX�����B�X�^�[�����ɍ߂�S�������t���邱�Ƃ��\��������Ȃ����A���ꂾ���ł͂Ȃ����낤�B�܂�A�鍑��`�Ɉ͂܂�āu�Љ��`���Ɓv���ێ����邱�Ƃ������ɕs�\���Ƃ������ƁA�����Ă�����x��Ă������{��`���Ƃ̊v���ł��������Ƃł܂��܂���@���[�܂������ƂȂǂ��l��������́u�Љ��`�v���v���ǂ�����ׂ������������Ă���悤�Ɏv����B
�����Ɋւ��ẮA�H���Ƃ��Ď��{��`��������Ƃ����������̘H���͈�ʐ��������̂������Ǝv���B���ꂵ���I�������Ȃ������̂��낤�B���⒆���͍��Ǝ��{��`�ƂȂ��Ă��܂������A���ꂩ�璆�����Y�}���ǂ̂悤�ɕώ����Ă������S������B20���I�����Ƀ\�r�G�g���V�A�����ʂ�������Ƃ͂܂��َ��ȍ�������A�����͕����Ă���Ɗ�����B
����I�Ǝv���邱�Ƃ́A���V�A�v���̎��s�Ŗ��炩�ɂȂ������Ƃ́A�v��o�ς͎Љ��`�̘H���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B����A���{��`���Ƃł����v��o�ς����Ă��鎞��ł���A���̌v�搫�͊�{���{��`�o�ς̃T�u���W�n�ł����Ȃ������̂��B������A���ꂩ��̎Љ��`���O�͕����l�ފw�I�Ȓm�������Ă����ׂ����낤�B�֓��K���������Ă��邪�A����肪�n���K�͂Ŗ��ƂȂ��Ă��鎞��ɂ́A�Љ��`�͈ꍑ�ł�������A��i���ł�������A�o�ϓI�ȉ��v�ł�������A�����I�ȉ��v�ł������肷��̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̈Ӗ��ł́A���{�͍ł��x�ꂽ�n��ł��邩������Ȃ��B�܂�A�l�X������̐�����������̗͂ō�낤�Ƃ��鎩���̏K�����ɂ߂ĒႢ���x���ɂ���B�X�o���o���ɉ�̂��ꂽ���̓��{�̘J���҂����Ă���ƁA���̊����Ђ��Ђ��Ɗ����A�����C���A���{�C���A�Ǘ��E�C���̐�����ς��Ă����Ƃ��납�炵���W�]���J���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�������_�ɂ�����}���N�X�E���[�j����`�ɂ��Ă̕]���Ƃ��̗��R�F
�}���N�X�Ɋւ��Ắw���{�_�x�œW�J����A����̃}���N�X�������̐��E�𑨂��Ă������_�ɂ͌���ׂ����̂������Ǝv���B���ɁA�u���l�_�v�ɂ��Ă͍����L�����낤�B�������A�S�N�ȏ���O�̗��_�ł���A���X�ÂтĂ��܂��Ă�����̂�����A���ꂩ���X�͔ނ̎c�������_�W������K�v������B�}���N�X�u��`�v�ɂ������l�X������悤�����A���̗���ɂ͎��͗����Ȃ��B����̐��E�����āA��������o������ׂ��ł����āA�}���N�X����o������̂ł͂Ȃ��B
���[�j���Ɋւ��ẮA�������_�Ƃ��Ă͂��͂�L���ł͂Ȃ��B�J�_������\�r�G�g�_�Ȃǂ͗��j�I�Y���Ƃ��č����P�Ƃ��ׂ��ł���B�����A�ނ̌��f�Ƃ��Ă̊v���ςɊւ��Ă͍��������Ă��邩������Ȃ��B���Ɏ����ނ̒m���Ɍh�ӂ������Ǝv���̂́A���V�A�v��������ɒ��ʂ��Ă������Ɍ����I�ȑI������ɂ��Ă������Ƃ��B�l�b�v���ނ̎��������ďI���������ƁA�X�^�[�����ɂ���ĕϐ߂��Ă��܂������Ƃ͕Ԃ��Ԃ����c�O�ł������B�����l�b�v�����̂܂ܑ����Ă���A���̒����̓˂��������Ă��鍢�20���I�����Ɍ���Ă�����������Ȃ��B�����Ȃ�A���j��50�N�͑��������N�ł��Ă����͂��ŁA���{��`���ƌQ�̐��̃P�C���Y��`�I�������Ɛ���Ƃ̍������܂�����ɓ����Ă�����������Ȃ��B���j�Ɂu�������v�͂Ȃ����A����Ȗϑz���������悤�Ȑ����Ƃł͂������B
�������_�ɂ�����u���{���Y�}�v�̕]���Ƃ��̗��R�F
�����Ɋւ��ẮA���͌��X������ۂ������Ă��Ȃ��B�m���ɁA60�N��̈ꎞ���Z�S���̗]�g�ŗl�X�ȓ}�I�ȕ�����o�����Ă���A���̍ۂɊ�Ȃȓ}�h�ᔻ�A���Ɏ������S�������u�g���c�L�X�g�v�Ă�肵�����Ƃɂ�焈Ղ������A�������Ƃ��V�������}�h���܂�����ȏ�ɓ}�h�ᔻ���Ђǂ��������Ƃ��l����A���オ�Ȃ���Z�ł�������������Ȃ��B�ނ��낱�̎����Ɋv�V�����̘H���▯������v���_�Ɋւ��ẮA���̌�̏��a�V�c�̕Ē�Ƃ̊m��Ȃǂ����J�������ɂ�A�����̎��_�����̐������������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ������낤�B
�܂��A���̋�������Ɍo�������J���g�������̕���ɍۂ��č�p�����u�������v�H���̊�łȔ�����`�������g�����������ɂ������Ƃ͐h���v���o�ł���B���́u�S�����v�I�����ʒu��g�����������Ɂu�������v�Ƃ��ė��p�������Ƃ͍����v���o�����B����ł͋��Y�}�V���p�̓����ƈꏏ�ɓ��������Ƃ��v���o���A��Ƃ��Ĉ�a�����Ȃ��������Ƃ͐\���Y���Ă��������B�Ⴂ���Y�}�V���p���u�S�����v�փ��X�y�N�g���Ă���Ă������Ƃ��v���o���B
���݂̓����̘H���ɂ͏ڂ����Ȃ����A�����ꎞ�����Y�}�̃I���O���Ă��āA���̎��ޏ����瑊�k������ۂ���͈������̂������Ȃ������B
�F�q���Ƃ̊W�ɂ��āi�R�{�`�����̒Q�����ǂ��������j
�������Ƃ̊W���F
���̎���́A���̎q�ǂ��̂��Ƃ������Ă���̂��A��ʓI�ȉ��̐���̂��Ƃ������Ă���̂�������Ȃ��̂ŁA�����ďq�ׂĂ��������B
���̎q�ǂ��͈�l���ŁA�ޏ������w�����w�N�̎��Ɏ����g���������o�����Ă���̂ŐF�X��J�������Ă��܂����B��������͔��R���ł��Ȃ茾���������������A�ޏ��̐l���ɑ��Ă͐e�Ƃ��ď\���ɂ��Ă��Ȃ������v���͂���B�������A�ޏ��͍��Z�𑲋Ƃ��Ă����Ƃ��o�āA��w���ƌ�A�E�܂ʼn��̎x�����Ȃ��Ɏ����őS�Č��߂Ă������Ƃ͗��h�ł���ƍ����v���Ă���B��w�ɂ͂킸���ł͂��邪�A���K�I�x���͂������A��{�I�ɂ͔ޏ����g���Ɨ����đS�Č��肵�Ă���B
���ł͔N�Ɉ��x������ł��邪�A��������Ƃ����l���������A�����I�ȗ�����͂����肵�Ă���B��w�ł͏����w���w�сA���݂͎��̃t�F�~�j�X�g�ł���A���̉^���ɂ��ϋɓI�Ɋւ���Ă���B��x�A�����Ńt�F�~�j�X�g�̕���ɗU���ĎQ�������Ă���������Ƃ����邪�A�ޏ��̒��ԂƂ�����Ęb���ƁA�F��������҂���ł���B���Ƃ͏��X����͈���Ă��c�_�ł���l��������ł������B
��ʓI�ɎႢ����ɂ��Ă��ꂱ��b�����Ƃ��N���͑������A��҂��܂��l���ꂼ��ł����āA��X�Ɠ��l�獷���ʂł���B�E��ŐV���������Ă���V�l�������܂����ꂼ��Ȃ̂����A���ł͋���ψ���Ӑ}�I�ɑ̈��n���̗p���Ă���̂ŁA�X���Ƃ��Ă͎Љ���ɑa���҂����������B�g���Ɋ��U���Ă��A����ς��狑�ۂ���҂����āA����������������B���������邱�Ƃ͐V�l�����̒��ł͏��������̕�����������҂��������A������ւ̊����͉s���l�������B���̎���A�����I�ɎЉ�^�����\�ʉ����ꂸ�A�\�w�I�ŕ����Ȃ����郍�[�}�Љ�I�ȃT�[�J�X���ۂ��������Ă���A�Ⴂ�l�����͂���ɑ傫���e������āA�Љ�I�v�l�͂�Ⴢ������Ă���B���̈Ӗ��ł́A���Ẳ�X�̎Ⴉ��������Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǎЉ�S�̂��Ǘ����ꓝ�����ꒂ���������Ă���Ɗ�����B���̏�A�Љ�̂��̂�ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����I�����̔��D������łł���B�^���_�Ƃł���������悤�Ȑl���ς��������Ă���B�����Љ�̎d�g�݂�m��Ȃ��������Ƃ͌����Ȃ��悤�ȁi����Ȃ�[�ւłȂ�Ƃ��Ȃ邪�j�A����̋������h���Ɗ����銴�����������Ă���B����͂����炭����Љ�̋ɂ߂čI���ȏ��ƌ��㕶���̂���悤�ƊW�����肻�����B�Ⴆ���̓T�^�I�Ȏ��Ⴊ���ȐӔC�_���B���̍l�����́A���ĉ�X�̎���Ɂu�����_�v������ɋc�_���ꂽ���Ƃ��l����A�u���̊�������B���Ă̎����Ƃ͐e���l�����̌Â��ƕ����I�ł��߉�Ȃ�����߂̋K���Â��߂̐��Ԃɑ��āA����l���Ă���ɑR�����鎩�Ȃ��`������Ƃ����Ӗ��ł������B�������Ԃ̏펯���L�ۂ݂ɂ��ĖفX�ƕt���]�������ł̓_�����Ƃ����Ӗ������ł������B���ꂪ�A���ł͎Љ�I�ȋ����Љ�ł̔s�҂ɑ��Ď��ӂ𔗂�c�_�ւƂ���ւ����Ă���B�����͐���������ꂸ�Ɍl�Ƃ��Ă̍Œ���̎����S���������Ԃ��K�͂Ƃ��Ă̎��ȐӔC�_���������Ă��錻��́A�����s��̐V���R��`�I�������������Ƃ������Ƃ����ł͐��������Ȃ��قǔߎS�Ȍ�����B�܂�����ŎЉ�I�����ҁi�����������̂�����Ƃ��āj�͎����̋��������܂��܂Ȏ��͂̉����������Ă����ł���̂ɁA�����̍ˊo�����ɓM���l�������B�����̂��Ƃ���A���݂̎�҂͂��Ĉȏ�Ɍ����������ɍĉ�Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ����B�����̍l���ʂɌ����āA��������͂������ɒ����Ƃ������ʂ̎Љ���͑��݂��Ȃ��B���͂ɋC���˂��Ȃ���A�����̍l�����Ђ��B���ɂ��A�ʂĂ͉��������̍l���Ȃ̂�����������Ȃ��Ȃ�悤�ȎЉ�Ƃ����̂͂��͂⎀�Љ�ł͂Ȃ��̂��Ǝv���B���݂̐E��ł͐����I�^�Љ�I�Șb��͋ɗ͊�������A���킢�̂Ȃ����Ԙb���d���̘b�����ł��Ȃ��l�������B�Ƃ�킯���I�ȏ�ʂł̓��c�̏ꂪ�ɂ߂ď��Ȃ��Ƃ����̂����̓��{�Љ�ł͂Ȃ����낤���B���߂�ꂽ���[���ɏ]���āA��������̂Ȃ����Ƃ������Ƃ����̂���l�̐��E���Ƃ����A���ĉ�X���������Ă������E�������܂����������Ƃ��đ��݂��Ă���B����ł͎�҂�����\�����瑶�݂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�������Ǝq���̐l���̔�r�F
���̎q�ǂ�����͂�����o�u��������ȍ~�̕X�͊�����ŁA���傤�ǎ����A�E���鎞�����Ζ��V���b�N����œ����悤�ɏA�E�悪�Ȃ���J�������A���݂Ɏ�������{�̘J���s��͍d���I�ő�w�𑲋Ƃ��鎞���ɏA�E����킷��Ɨ]���̍K�^�Ɍb�܂�A�l��{�̓w�͂����Ȃ������̐l�������肳��Ă��܂��悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��āA�������Ȃ��J�����悤���B��ʓI�ȘJ���Ґ��т̎q�ǂ������ɂƂ��č��̓��{�͖{���ɕ�炵�ɂ����Љ�ł͂Ȃ����낤���B�q�ǂ��̐l���Ƃ̈Ⴂ���l���鎞�A���̈���Ă�������w�i�Ǝq�ǂ�����������Ă�������w�i���Ⴂ������̂ŁA��T�ɔ�ׂ邱�Ƃ��ł��������Ȃ��B�������w���̍��͂܂����Ŏs�I���i���c���Ă��āA���X�X�ɂ͏��w�R�l����������Ă������A�����m���ƁX������Ă����B���͖��ܑ��œy���@��Ԃ��ăr�[�ʗV�т�������A���������ɂ���n�œy�܂݂�ɂȂ��Ĕ��|�V�т��������̂����A����ȕ��i�͍���ǂ��ɂ������Ȃ��B�w��������w�N��20�߂���������X�̎���͊X�Ɏq�������Ă����B���͐������ꂽ�����֍s���Ă��V��ł���q���͂���ق猩���邾���ł���B����قǂ̒Z���ԂɌ��ς����Љ�ł͎q�������̈炿�����ׂ邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����B���{��`�̋���Ȑ��Y�͎͂��X�ƐV�����Z�p�ƎY�Ƃݏo���āA�~�]�̕����܂܂ɔ������Ă������A�{���l�Ԃ���ߒ��͎��R�ߒ��ł����āA�������Ƃ������̂��B���̐l�Ԃݏo���A��ĂĂ����ߒ������͎��{��`�ɂ͂ǂ����悤���Ȃ����A�@�B���ł����Ɏ��R�ߒ��ɔC���邵���Ȃ��B���̖��������̓��{�ɁA���邢�͐��E���ŋN�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�l�Ԃ̐������x����Y�Ɖߒ���l�Ԃ̎��R�������ɓK��������悤�Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ����ɋ��߂��Ă���悤�Ɋ�����B